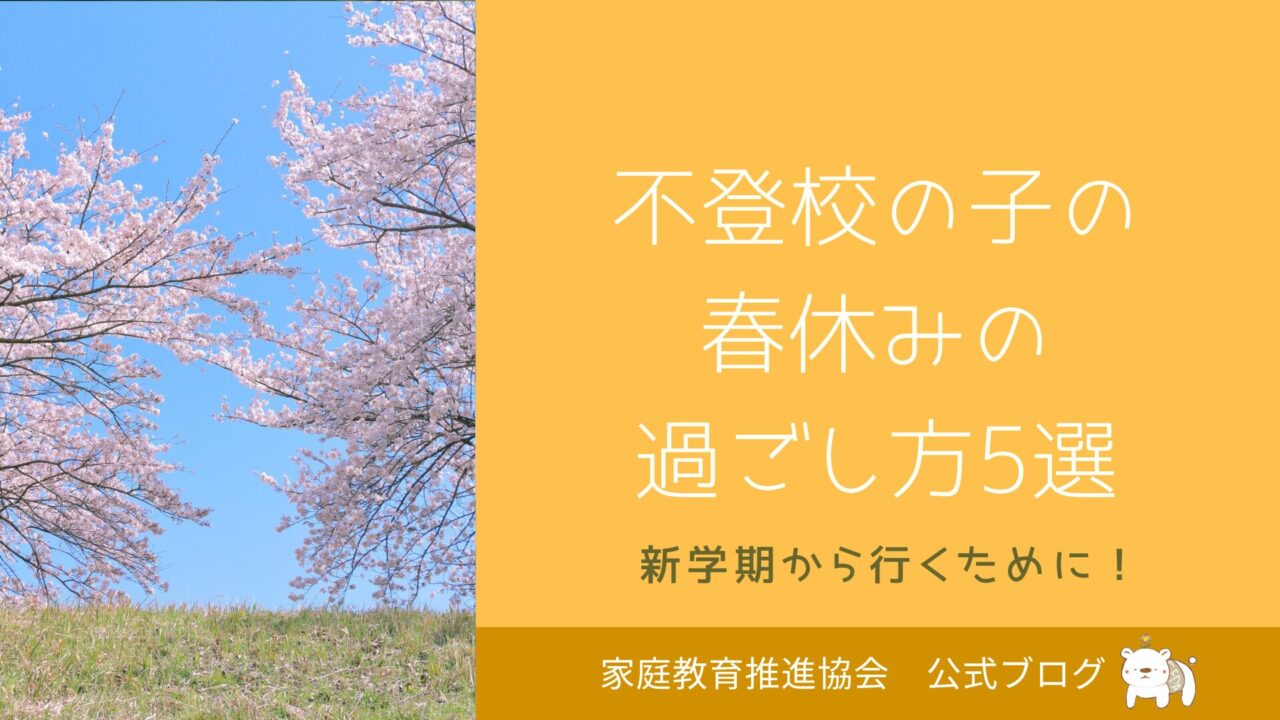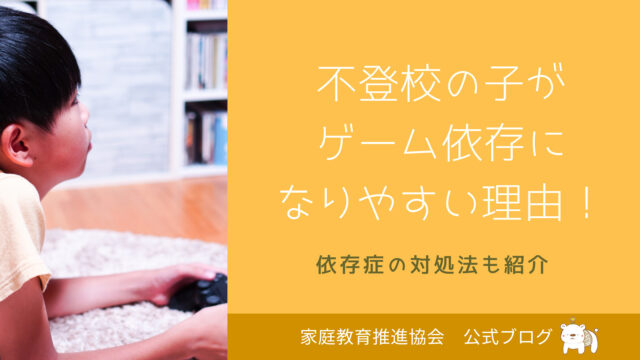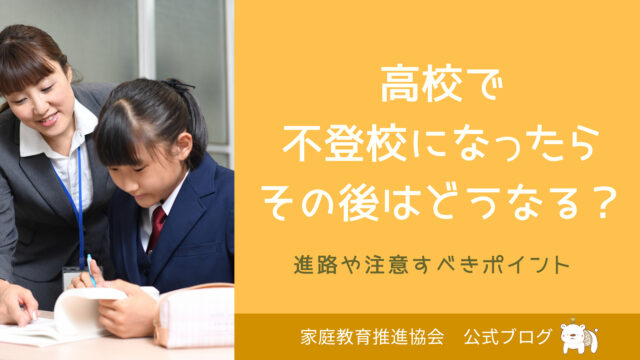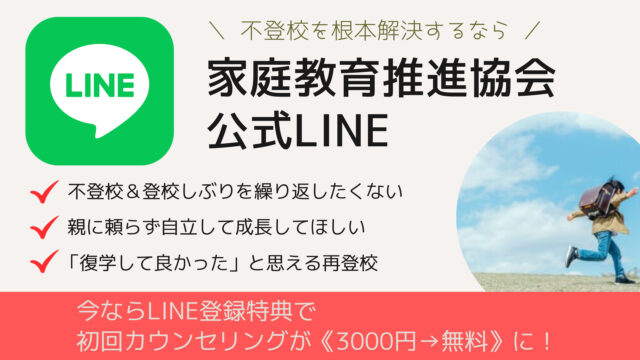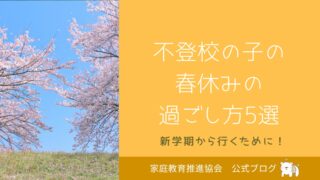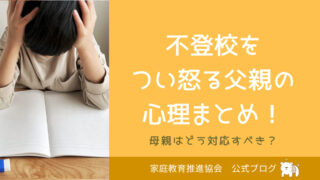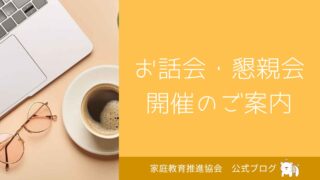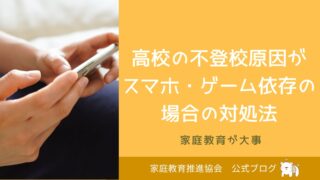新学期目前の春休み。
不登校のお子さんを持つ親御さんにとっては、特に焦りや不安が募る時期かもしれません。
今回は、家庭教育の視点から、不登校の子どもと向き合うための具体的なポイントを5つに分けて詳しくお伝えします。
【新学期から行くポイント①】生活リズムの立て直し

春休みは、子どもたちが新学期にスムーズに移行するための重要な準備期間です。
特に不登校のお子さんは、長期休み中に生活リズムが乱れてしまいがちです。
昼夜逆転を防ぐために、起床や就寝時間、食事のタイミングを一定に保ちましょう。
親:「春休みだけど、朝ごはんは8時に一緒に食べようね」
子:「え~、めんどくさい」
親:「朝一緒に起きて食べるだけでも、気分が違うと思うよ。少しずつ慣れていこう」
親子で話し合いながら計画的な日課を作ることで、子ども自身も生活にメリハリが生まれ、新学期の登校への抵抗感を軽減できます。
【新学期から行くポイント②】「過干渉・過保護」に注意

不登校の親が焦ってついやってしまう失敗の代表例が「過干渉・過保護」です。
例えば、以下のようなやり取りはよくあるケースです。
母:「4月からは学校行くの?」
子:「行かない。」
母:「また行かないの?いつになったら行くつもり?」
子:「……(無言)」
母:「スマホばかりしてるからダメなのよ。少しは外に出なさい!」
こうした会話は子どもにプレッシャーを与え、逆効果です。
焦りや不安を感じるのは自然ですが、少し距離を取り、子どもが自分で動き出す機会を与えましょう。
【新学期から行くポイント③】第三者の目線で子どもを見直す

親として子どもが心配で「私がなんとかしてあげなきゃ!」と近すぎて、知らず知らずに母子依存の関係になっているかもしれません。
母子依存関係では客観的な判断が難しい場合があります。
家庭教育支援の中でも、当たり前のように子どもにしているサポートに対し「お母さん、この行動は彼女の自立や考える思考をストップさせてしまっていますよ」とアドバイスすることが多くあります。
「アドバイスを頂きよく考えてみたら先生のおっしゃる通りですね。」このように返事が返ってくるのも日常茶飯事です。
こうした第三者のアドバイスを取り入れることで、新しい気付きや冷静で適切な対応ができるようになります。
【新学期から行くポイント④】一人で抱え込まない

文部科学省が2025年2月に公表した最新データによると、不登校の児童・生徒数は約32万人と過去最多を記録しました。
特に中学生が多く、社会的にも深刻な課題です。
不登校は特別ではなく、どの家庭でも起こり得る問題として受け止める必要があります。
1位:学校に行かせるべきか悩む
2位:子どもの将来が心配
3位:子どもとの接し方が分からない
4位:自分の育て方に自信が持てない
5位:周囲からの目が気になる
このようなランキングから、多くの親御さんが同じ悩みを抱えていることが分かります。
一人で抱え込まず、安心して子どもとの向き合い方や関係改善の方法を考えるきっかけにしてみてください。
【新学期から行くポイント⑤】家庭教育の重要性を再確認

家庭教育は子どもの心の基盤を築く重要な要素です。
特に不登校のお子さんは親子での会話が少なくなる傾向にあり、学校の話をしょうとしてもできない事が多いので、家庭で安心して会話ができる関係になることが第一歩となります。
親子の会話では子どもの趣味への共感、お互いにリラックスした時間を積極的に取り入れましょう。
日常のささやかなコミュニケーションが、子どもの自己肯定感や安心感を育て、新学期を前向きに迎えるための準備を助けます。
「新学期に好スタート!不登校時の春休みの過ごし方5選」まとめ

春休みは親子で落ち着いて準備を進められる大切な時間です。
焦らず、子どもとの信頼関係をじっくり育てていきましょう。
自分だけで判断が難しい場合や対応に悩んだ際は、ぜひ家庭教育推進協会の電話カウンセリングをご活用ください。
現在、【LINE登録で初回電話カウンセリング無料キャンペーン】を実施中です。家庭教育の専門家と一緒に、お子さんと向き合う方法を見つけていきましょう。